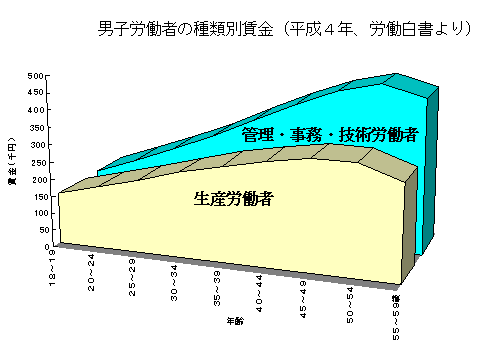
ITによる製造間接部門の生産性向上とナレッジマネジメント
大阪産業大学 長坂悦敬
1.はじめに
産業構造が大きく変化しサービス業に従事する人の割合が増加している今日、いわゆるホワイトカラーの生産性向上はたいへん重要なテーマである。とくに製造業においても間接部門の比率が大きくなり、そのコストを低減するための努力が行われている。製造間接部門の生産性向上に関する従来の研究は、大きく2つのカテゴリーに分類される。一つは、システム環境(情報システムなど)や人的環境(組織、風土など)の改善、改革による生産性向上であり、もう一つは、製造間接部門の生産性測定と管理からコスト低減を実現しようとするものである。ここで、生産性評価について効率だけでなく業務によって生み出される付加価値を含めて議論されなければならない。また、システム環境の整備においては個人および組織における付加価値創造が助長される仕組みが必要である。
ここでは、まず製造間接業務および間接費の取り扱いの実態を把握する。さらに、ITによる製造間接業務コスト低減のための方法とつまり、効率化とナレッジマネジメントとを両立させるための具体的な方策を検討する。
キーワード: 「製造間接費の配賦問題」、「ABC/ABM」、「BPRの具体化」、「BPRと知的資産管理との両立」、「ITによる付加価値の計測・評価への期待」。
2. 間接業務の特徴と問題点
一般に、製造業で直接業務に対して言われる間接業務は、主に(1)管理業務、(2)スタッフ業務、(3)事務業務の3つに分かれる(秋山兼夫、1993年)。
(1) 管理業務
管理者のみならず担当者自らが行う知的業務で、計画・実施・統制・評価に関する業務や情報収集および状況判断に関する業務、意思決定に関する業務、部下の動機付けや育成に関する業務などが含まれる。上位管理者になればなるほど非定型的で統制的な業務が多くなる。
(2) スタッフ業務
専門家の行う業務で、経営者や上位管理者を支援する。企画や管理に関する業務、人事・総務・経理に関する業務、研究・開発・技術などに関する業務など。
(3) 事務業務
各部門において事務的な活動を行う業務で、何らかの形で種々の情報を扱い、定型的あるいは非定型的に処理し、帳票に書き出したりコンピュータデータとして保存する。
直接業務と間接業務を比較すると例えば図表1のようになる。直接業務では、定型作業が多く、個数とか作業量で生産性を測定することが比較的容易である。また、TQCに見られるように生産向上運動や小集団活動が広く定着していて、生産性改善手法が多種多様に確立されている。一方、間接業務は非定型作業であり、生産性についての評価尺度を定義することは難しい。企画、開発、研究、技術などの知的業務においては、「データ収集」、「情報分析」、「意思決定」、「行動」の4つのカテゴリーが順々に行われ、それが繰り返されていく。具体的な業務は、新製品の開発に関する企画、開発計画、マーケティング活動であったり、受注された製品の原価計算や生産設計・量産準備業務であったり様々である。しかし、いずれにしても、何らかの形でデータを収集し、情報を分析すると同時に、目標を定めて、スケジュールを立て、業務を進めていく。そのとき、コミュニケーションによって関連のメンバーと情報を共有する必要がある。また、途中で、考えを整理したり、伝達しながら、最終的に、報告、提案して、意思決定へ結びつける。企画書、計画書、図面、報告書、提案書、PRリーフレットなど多くの帳票は、知的業務の結果をひとつひとつ形にしたものである。これら業務の「質」、「付加価値」を高めることが必要である(長坂悦敬、1998年)。
図表1 直接業務と間接業務の特徴比較 (秋山兼夫、1993年)
| 直接業務 | 間接業務 | |
| 内容 | 肉体的生産活動 | 知的生産活動 |
| 進捗管理 | 容易 | 困難 |
| 繰返性 | 多い(定型) | 少ない(非定型) |
| 評価尺度 | 明確 | あいまい |
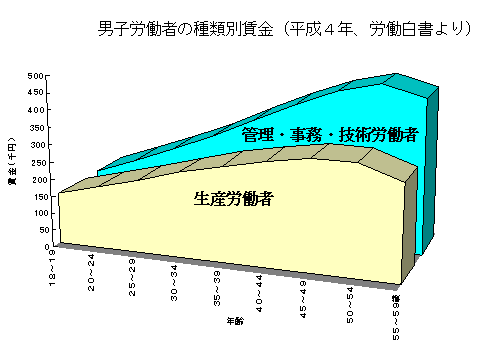
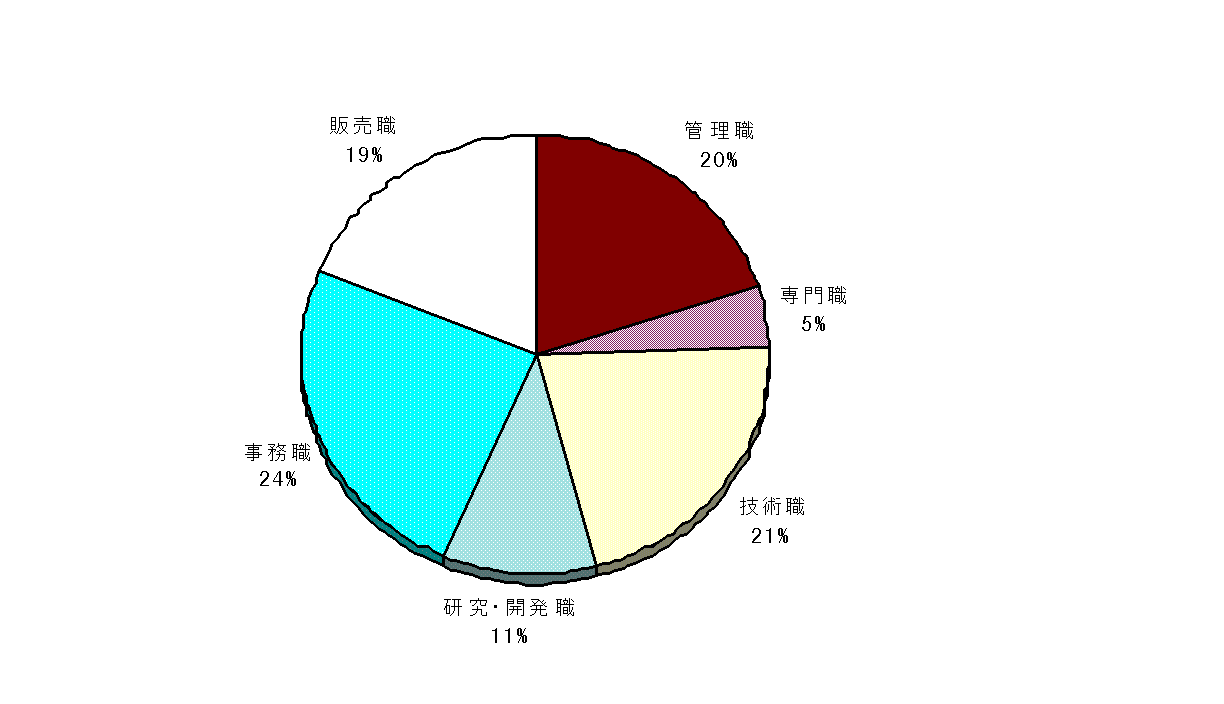
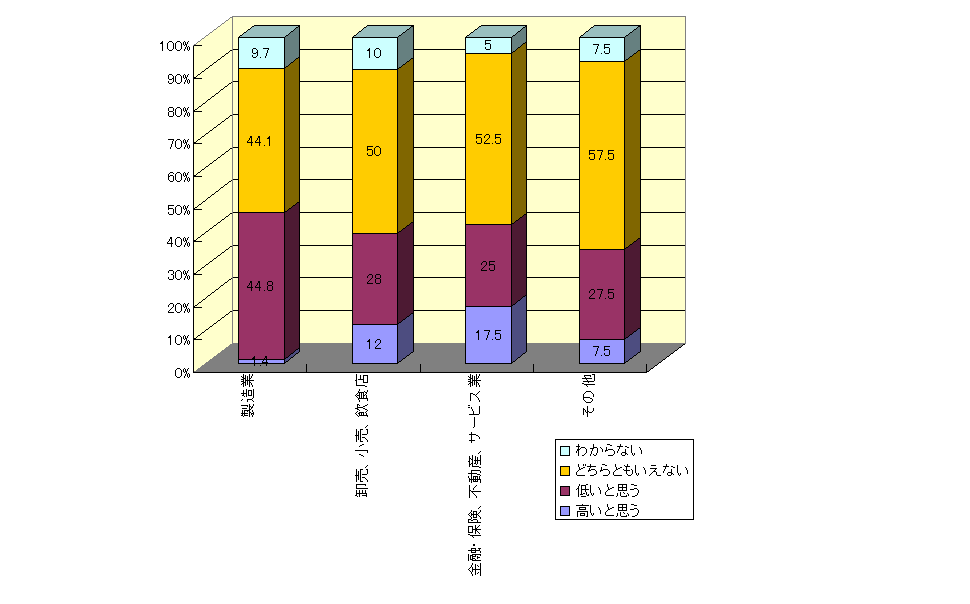
ホワイトカラーの生産性について行われた調査結果(雇用情報センター、1994年)の一部を図表2~4に示す。図表2にあるように国内製造業では階層別労働賃金には明らかに格差が生じ、既に平成5年のアンケート調査において製造業での間接業務の生産性が低いという意識が44.8%と約半数にのぼった(図表4)。また、研究・開発・技術職の必要性については多くの企業がその存在意義を認めているにもかかわらず、労働者の質が望ましい水準に達していないと感じる職種では、圧倒的に研究・開発・専門職をあげる企業が多いという結果になっていることに注意しなければならない。
製造業では従業員の構成比が明らかに変化している(図表5)。世の中が量的拡大志向から高付加価値化へと転換したこととバブル崩壊後の景気後退は過剰雇用を浮き彫りにした。これが現在間接業務の生産性を多くの企業で問題にしている背景であると説明されている(福谷正信、1995年)。また、製造原価に対する経費の増加は著しいことが個別の企業のデータからもわかる(図表6)。
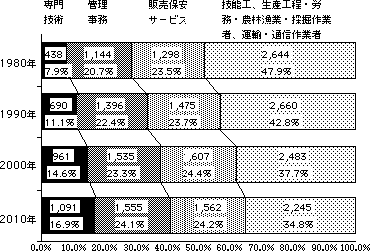
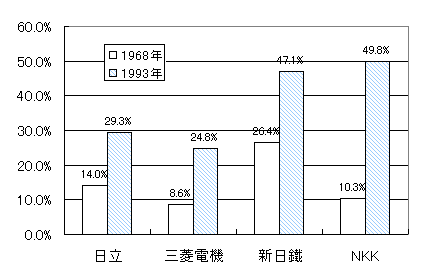
日本人は集団を形成し、閉じた共同体の中で濃密につきあうことを好む。つまり、協調性を大切にする一方で、突出するものを嫌う。この集団への盲目的な帰属観念が強く、減私奉公的価値観が賛美されることは非効率の原因のひとつである。高い効率や生産性は制約があるところから生まれる。減私奉公を要求される環境ではどうしても効率が悪くなる。したがって、終身雇用制度、年功序列制度も雇用と報酬に対する制約がないという点では非効率を生む原因のひとつであると指摘された。従来の雇用形態と報酬制度がくずれ、会社に対する従業員の帰属意識は下がった。ホワイトカラーのインセンティブ(意欲の源泉)を確保する取り組み、例えば、制度改革として成果主義型の給与体系、奨励制度(チャレンジ賞)、社内公募制、ストックオプション(自社株購入権)の導入などが進められている。しかし、日本の社員はお金だけでは本気で働く気にならないという指摘もあり、「やりたい仕事を納得してやれば、すごいエネルギーが発揮される」という特質をどのように生かすかを真剣に考えなければならない。
実際に企業がこれまでに重視したいわゆる「ホワイトカラー」の生産性向上策は「OA化、情報システム化の推進」であるという回答がもっとも多く、続いて「不要・不急な業務の削減」、「会議の効率化」、さらには、「本社や管理部門の要因削減」、「業務のアウトソーシング」と続く(矢矧晴一郎、1994年)。実際にどの程度のコスト低減が図れ、生産性がどうなったかを知るためにはコスト計算が正確に行われなくてはならない。つまり、社会の産業構造の変化によって「知的生産性」というものが重要視されているが生産性の測定、評価方法は確立されていない。しかし、製造業では相対的にその生産性が低いと感じられていることが明確である。知的生産の結果が再利用され、評価されるシステムが望まれる。
3.間接費の取り扱いと効率化へのアプローチ
3.1 間接費の取り扱い
一般に原価は製造原価と販売費、一般管理費からなる。さらに、製造原価は材料費、直接労務費、経費に分けて考えることができる。近年、工場を自動化することによって、直接労務費が現象する代わりに製造間接費が相対的に増大してきた。また、自動化設備の運用と保守に関連した支援コストがかかり、製造間接費の絶対額が増加している。つまり図表6に示すように経費(外注加工費を除けばほとんどが製造間接費)の割合が急激に増えてきた。間接費の上昇は、(1)エンジニアリングコスト(工場支援、管理、サービス関連の人件費)、(2)ポリシー・コスト(研究開発費など)、(3)オペレーティング・コスト(物流費など)、(4)コミッテッド・コスト(建物、機械、設備などの減価償却費)に分けて議論されているが(櫻井通晴、1995年)、とくに工場の自動化の代償として増加が激しいエンジニアリングコストを低減することが望まれている。
コスト低減のためにはまずコストを正確に把握しなければならない。過去に行われた調査 (NAA東京支部会、1988年)では、製品原価計算制度に対して製造間接費の配賦計算に対する不満をあげる経営者が多いことが指摘されている(櫻井通晴、1995年)。そこでは、間接費の配賦計算の改善を目指すと回答した企業が54%に達した。そのために(1)直接原価計算へ移行し原則として間接費配賦の必要性をなくす取り組み、また、(2)全部原価計算の枠組みの中で製品または製品系列別の直課によって配賦そのものを減少させ恣意性を排除する取り組み、さらには、(3)やはり全部原価計算の枠組みの中で配賦の方法を変えていく取り組み(マン・レートからマシン・レートへの移行など)が行われた。そして、(3)の配賦方法の抜本的な見直し方法としてABC(Activity Based Costing)が提案されるに至る。
1995年に行われた国内の上場企業581社に対する製造間接費配賦システムの調査(渡辺岳夫、1995年)に対する考察によると、全部原価情報を必要とし生産構造の複雑性から製造間接費の原価構成に占める割合が高い企業群が存在し、それらにABCを適用する意義が高いことが示唆されている。
ABCでは、資源から活動、活動から製品に製造間接費を跡づけていく資源の原価を活動センターまたはコストセンターに割り当てるための資源作用因は伝統的原価計算での部門個別費と部門共通費を製造部門と補助部門に配賦するための基準に相当する。さらに、活動センターまたはコストセンターの原価を製品に割り当てるために活動作用因が用いられる。伝統的な方法では、マン・レートやマシン・レートが用いられてきた。製造間接費を発生させた原因は原価作用因(コスト・ドライバー)と呼ばれるが、それは活動作用因に限定して用いられる。帳票の枚数、工程設計の時間、図面変更回数、処理量など原価作用因を明確化して計測することが必要になる。できるだけ細かくしかもリアルタイムに原価作用因を計測して分析できればABCを適用する意味が出てくるが、計測すること自体に手間、コストがかかりすぎるために実際には運用しにくいという問題点が指摘された。
3.2 間接業務効率化へのアプローチ
原価計算の目的には、(1)財務諸表のための棚卸評価、(2)業務管理、分析(3)製品、製品系列、顧客別の収益性分析などがある。複数の原価があれば有効であるという意見と実務ではかえって混乱するという意見がある(櫻井通晴、1995年)。
実際の日米の間接費の扱いについての差異も指摘されている(櫻井通晴、ロビン・クーパー、1990年)。すなわち、日本の経営者が求めているものは、正確な配賦よりも、配賦をできるだけ少なくし、原価管理に役立つ情報である。活動に志向した原価情報を得ることにより、原価管理に役立てたいと考えている。従来、多くの企業で製品系列別に製造間接費を直課しようとしていたのは、そのほうが原価管理に役立つからである。一方、米国の経営者は正確な製品原価情報を求め、製造間接費の正確な配賦を求めている。それは、原価情報が製品の収益性分析に役立つからである。アメリカの経営者は株主からのプレッシャーが強いため、できるだけ収益性の高い製品を生産・販売しようとする。他方、日本の経営者は、長期的な企業の存続を第一に考えるため、収益性の計算結果だけで企業の戦略を決定するようなことはない。顧客との長期にわたるつきあいを大切にするため、収益性が多少悪くても、当該製品系列の生産・販売を継続しようとする。たとえば、製品系列別直課を行う目的は、製品の多様化にともない、個々の製品の原価を正確に把握することは煩雑すぎるということがある一方、直課を多くすることで原価管理を容易したいというねらいがある。価格は原価のみによってきまるのではなく、市場の要因が大きい。しかし、米国の会計専門家の間では、原価が価格に相当大きな影響をおよぼしているとする根強い信念があり、ABCの基礎には原価をもって価格戦略に役立てたいという明確な意図がある。
したがって、日本企業ではABCを原価計算システムとして採用せず、むしろ生産管理者のツールとして役立ててABM(Activity Based Management)へ展開するという傾向がある。ABCをBPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)のツールとして活用するアプローチ、ABMは、例えば図表7のように表される(櫻井通晴、1995年)。
図表7 ABCとABMの関係(出所:櫻井通晴「間接費の管理」)
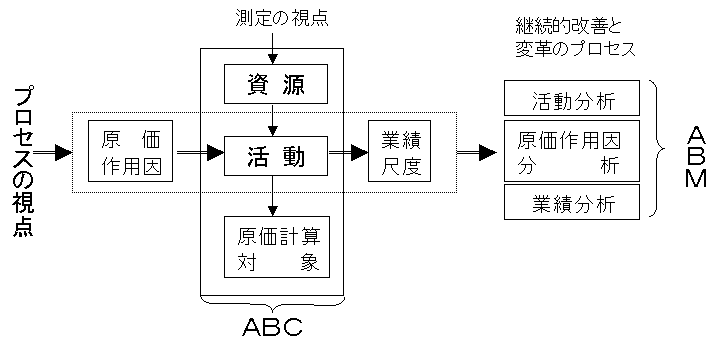
4.ITによる間接業務コスト低減活動
ABC/ABMアプローチでは、<1>ビジネスプロセス分析、<2>プロセス・アクティビティの定義、<3>プロセス・アクティビティ別原価集計、<4>プロセス価値分析、<5>改善案の作成という5つのステップで改革案の捻出が行われる。このアクティビティー分析では、アクティビティーを細分化したプロセスのレベルで業務フローを記述した後、プロセスを処理時間ばかりでなくコストとして定量的に把握する。つまり、各プロセスについて付加価値を生むものかどうかを検討し、その価値(V)は、機能(F)/コスト(C)の算式で表され、コスト低減余地(C-F)を計算し比較することができる。アクティビティーの分類は、例えば、2区分(付加価値活動と非付加価値活動)または3区分(コア、支援、付随アクティビティー)などに分けられ、吟味される。一般的なアクティビティーの割合は、コア30%、支援35%、付随35%であるといわれている(橋本賢一、1996年)。
実際の業務に適用する場合のABMでの課題として、「価値Vの定量値をどのような基準で算出するか」、また、「アクティビティごとの工数に関するデータをどのようにして収集するか」がある。このような価値分析自体は目的ではなく、業務改革案を考え出すための手段であると言える。従って、ABMのためとはいえ、ABCにコストをかけ過ぎることはできない。また、ABMではABCから発信される注意喚起情報から非付加価値情報を摘出し改善していくという帰納的なアプローチであり、これ以外に演繹的に抜本的な改革案を創出する切り口も必要である。
4.2 ITによる製造間接部門コスト低減方法
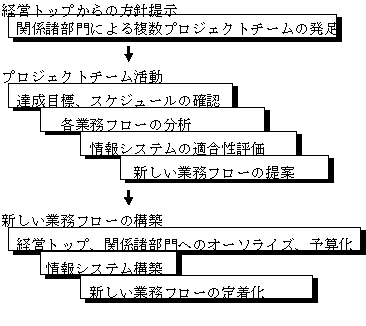 生産構造の複雑性に起因して段取費、注文処理費、仕様書作成費、製造スケジューリング費、製品設計費などは増加する一方であり、ここでは具体的な製造間接部門のコスト低減方法を以下のように考え、実際に活動をおこなった(長坂悦敬、1997年)。その方法論の概要を図表8に示す。
生産構造の複雑性に起因して段取費、注文処理費、仕様書作成費、製造スケジューリング費、製品設計費などは増加する一方であり、ここでは具体的な製造間接部門のコスト低減方法を以下のように考え、実際に活動をおこなった(長坂悦敬、1997年)。その方法論の概要を図表8に示す。
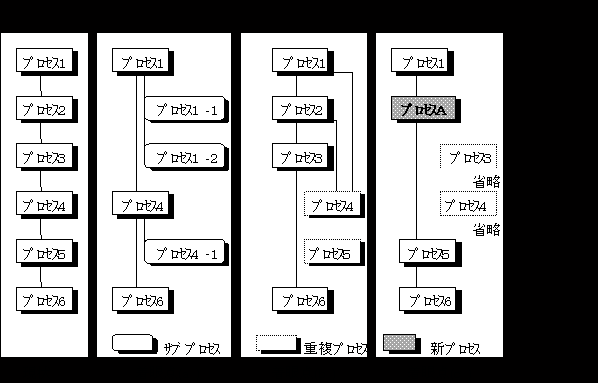
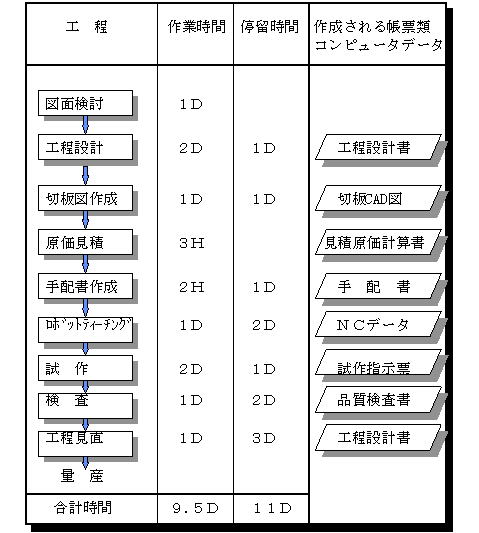 業務分析においては、「プロセスに注目する」ことを念頭に、3つの着眼点を用意し、帰納的および演繹的に各業務のフローを徹底的に分析する。業務フローの記述においては、各組織でどの業務を担当しているかではなく、その生産のためにどのようなプロセスが行われているかを図表9のような業務フローチャートとして詳細に記述する。このとき、書式はとくに問わないものの、平均作業時間、停留時間、その各プロセスでのアウトプット(帳票やコンピュータ入力されるデータ)についてとにかくありのまま列挙することが重要であると考え、しかもすべてを計測するのではなく複数人の専門職へのヒアリングによってその専門職の代表者が作成する。業務フローの分析方法は次のとおりである。すなわち、以下のような着眼点(a)、(b)、(c)を用意し、業務フローチャートを書き換えていく(図表9参照)。着眼点(a)、(b)は、帰納的な分析方法であり、(c)は演繹的な分析方法である。
業務分析においては、「プロセスに注目する」ことを念頭に、3つの着眼点を用意し、帰納的および演繹的に各業務のフローを徹底的に分析する。業務フローの記述においては、各組織でどの業務を担当しているかではなく、その生産のためにどのようなプロセスが行われているかを図表9のような業務フローチャートとして詳細に記述する。このとき、書式はとくに問わないものの、平均作業時間、停留時間、その各プロセスでのアウトプット(帳票やコンピュータ入力されるデータ)についてとにかくありのまま列挙することが重要であると考え、しかもすべてを計測するのではなく複数人の専門職へのヒアリングによってその専門職の代表者が作成する。業務フローの分析方法は次のとおりである。すなわち、以下のような着眼点(a)、(b)、(c)を用意し、業務フローチャートを書き換えていく(図表9参照)。着眼点(a)、(b)は、帰納的な分析方法であり、(c)は演繹的な分析方法である。
(b) 重複プロセスの摘出
(c) 新プロセスの組込
図表9の着眼点(c)で示すように、新しいプロセス(とくにITを駆使したプロセスを創成し(図表9着眼点cではプロセスA)、組み込むことで他の複数のプロセス(図表10着眼点(c)ではプロセス3、プロセス4)を省略する、あるいは大幅に改善することを狙ったことを示す。このとき、ITの成熟度を評価して、その適用性を検討することが重要である。既存パッケージソフトウエアが適用できるもの、既存パッケージソフトウエアをカスタマイズすれば対応できるもの、新たにソフトウエアを開発すべきものと整理される。
ここでのITによるコスト低減活動の特徴は、M.Hammerらのトップダウン型、劇的なBPRの進め方(M.Hammer and J.Champy、1993年)に対して、ミドルアップ型、漸進的な進め方を適用したことにある。ただし、その背景には経営トップの理解とリーダーシップが必要であることは言うまでもない。図表11に典型的な産業機械メーカーでの製造部門の間接業務の内容を示す。直接/間接人員比は7:3であった。実際に上記のコスト低減活動をおこなった結果15%の製造間接部門の工数を削減することができた(長坂悦敬、1997年)。
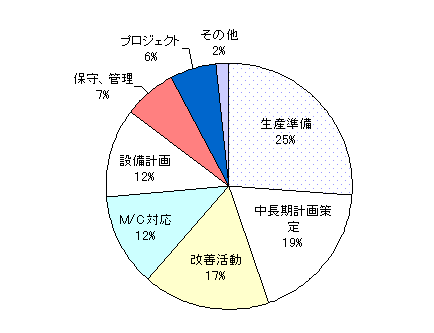
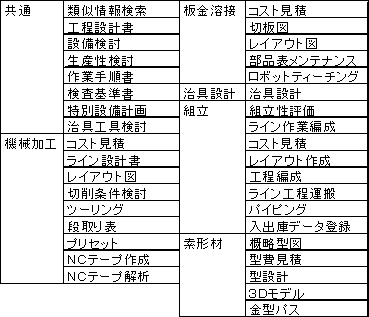
図表11 典型的な産業機械メーカーでの間接業務の内容
4. 製造間接部門における効率化の追求とナレッジマネジメントの融合
BPRによって効率化を追求した業務フローは「業務をデジタル化すること」がベースになっている。デジタル技術で非定型業務を定型業務に変えブラックボックス化していくことが効率化につながる一方で、結果的に仕事のやり方を熟知しているベテランがいなくなり、業務が滞る、いわゆる「コーポレート・アルツハイマー(企業痴ほう症)」の問題が危惧される。これは、一方で、ノウハウ、固有技術でモノ作りの競争力を保っていた日本企業がデジタル化によって比較優位を低めつつあるという指摘につながる。
これに対して、経営問題、例えば社員能力の向上、効率的・効果的な研究開発、顧客満足度の向上などにかかわる諸問題の解決策として、業務を定形化しデジタル技術に置き換えるというアプローチに加え、経営資源としての知識をいかにして獲得・創造・蓄積・活用するかを考えるべきであるという指摘が起こっている。野中郁次郎教授が発信した組織的知識創造の理論、いわゆる「ナレッジマネジメント」はそのひとつの方向を示すものである。
企業や地域や国家の競争力の源泉として知識が注目されるようになってきたのは、1990年代に入ってからであろう。この年にはアルビン・トフラーが『パワー・シフト』で、「知」がグローバルな経済・経営や政治・軍事での力関係の変化に決定的な役割を果たしていると論じた。ピーター・ドラッカーも、『ポスト資本主義社会』(1995)で、資本主義の後に来る「知識社会」では知識が「ただ一つの意味ある資源」であると主張した。ナレッジマネジメントの背後には、このような知識の重要性への共通認識がある。
知識とデータ、情報との違いを再認識しなければならない。データは、いわば数字の羅列のようなものであり、そのままでは意味を持たない。データを分析することによって出てきた意味が情報である。それがすでに所有していた知識に変化をもたらすことで、我々の判断や行為のよりどころとなる。情報が行為によってひき起こされたフローとしてのメッセージであるのに対して、知識はその行為すなわち経験の反省を通じて蓄積されたストックとしての情報体系であり、それは善悪などの価値観や好き嫌いなどの情念と強く結び付いている。
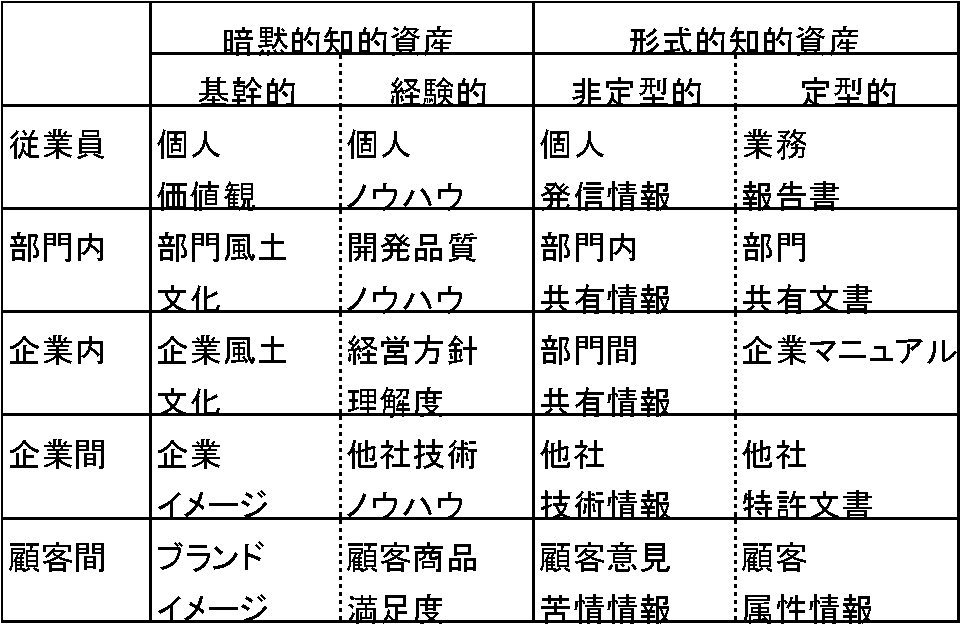
知識は、ノウハウなど、五感を通じて獲得された個人的な身体知・経験知であり、言葉や数値で表現しにくい「暗黙知」と教科書やマニュアルに載っている客観的・明示的な「形式知」に分けて整理できる(図表12)。形式知は、言語化・数値化・図表化されているので情報技術で扱うことができる。ここで、従来の効率化を追求した業務フローに対して考慮されるべき点として、既存の形式知の共有・活用と同時に個々の社員の暗黙知を形式知に変換して組織知にすることが挙げられる。知識は人に教えても無くならないし、かえって他の人の知識と異種交配して増殖する性質を持っている。そういう意味でも、同じ組織の中では自分の持っている暗黙知、とくに自分の体験から得られたノウハウを積極的に公開して共有できる仕組みをつくることが重要である。
製造間接部門などホワイトカラーの生産性を評価する際も、従来の工数だけでなくアウトプットの付加価値をどのように計測するかが問題となる。これは、非財務的尺度と財務的尺度の両者を考慮した「総合的マネジメント」の必要性が強調される根拠のひとつともいえる。ホワイトカラーの活動での生産性とは,一体どのようなものなのであろうか.吉田によれば2つの見方がある。第一に,生産性は業務遂行の成果/投入資源によって計算される.その場合,投入資源一定の場合は成果の大小が,あるいは成果が一定の場合は投入資源の大小が,生産性の値となる.ただし,成果の測定は困難な場合が多く,その結果として,生産性の測定には,投入資源量が利用されることが多かった(アンダーセン,1997). 第二に,生産性は,「業務遂行の成果/最高水準成果」という式によっても導き出せる。最高水準を規定するための手法としてベンチマーキングがある.ここで成果として産み出される物とはいったい何かということを明確にしなければならない。
実務での総合的マネジメント実現のためにバランスト・スコアカードやTPマネジメントが開発され、適用されている(浜田和樹、2000年)。個別目標が細かく設定され、総合目標に対する寄与率も数値で示される。業務目標や革新的目標と呼ばれる目標の中にも非財務的目標と財務的目標がバランスよく含まれていることが望まれる。これらはアウトプットの付加価値計測に有効である。さらに一歩進めて、目標を達成するために行われたプロセスに内在する暗黙知を掘り起こし、資産として共有・再利用できるツールが必要である。
5.製造間接部門の業務支援情報システム -効率化と知的資産増幅を目指して-
5.1 製造間接部門の業務支援情報システムの要件
コスト計算、金型や治工具の設計、購買品の手配、工程設計、生産計画などの製造間接業務は相対的に増加しているが、固有技術に依存するところが多く、同一企業内であっても意思決定のために必要な背景情報は担当者ごとに異なっているという問題がある。つまり、コスト低減のための効率化とともに情報の共有や伝承に対する具体的な取り組みを行う必要がある。そこで、製造間接業務をモデル化して編集、登録しながら、意思決定の背景にある多様な情報のデータベースと関連づける方法論について検討した。
ナレッジマネジメントのタイプは図表13にあるように大きく4つに分けて整理されている。これら4つのタイプはそれぞれ独立したものとしても組み合わせたものとしても展開できる。とくにベストプラクティス型はナレッジマネジメントの典型で基本的には持てる知識資産を形式知として集約し再利用しながらスパイラルアップしようとするものである。
図表13 ナレッジマネジメントの4つのタイプ(野中、紺野による)
タイプ |
要点 |
実現の課題 |
| ベストプラクティス共有型 | ・過去の問題解決法の共有 ・業務の重複排除、ベストノウハウ複製による時間・コスト短縮、削減 |
・共有への意識改革 ・継続性 |
| 専門知ネット型 | ・社員、専門家の知識のディレクトリー化 ・適材・適所・適時に結合 |
・ネットワーク上での対話の仕組みと組織文化 ・個々人のイニシアティブ |
| 知的資本型 | ・知識資産を把握・活用・展開するための分類の組織的方法 ・ポートフォリオ、フレームワーク |
・静的なストックとしてでなく、動的なプロセスとして知識資産の活用ができるか |
| 顧客知共有型 | ・顧客との知識共有、知識提供の場づくり | ・顧客にとっての価値は何か ・顧客との継続的進化の仕組み |
つまり、以下のようにステップを進めながら結果としてベストプラクティスの知識を使うことによる新たな知識創造を狙う。
(1)暗黙知の形式知化 → ナレッジデータバンクの整備
(2)知識共有のインフラ整備
(3)知識学習組織の確立
(4)知識の定期的な棚卸し
従って、間接業務をモデル化し、各プロセスに関わる背景情報のデータベースとリンクして、業務担当者の判断根拠が負荷の少ないオペレーションで蓄積されるような情報管理システムを開発することが必要となる。ここで、製品情報などの基本的なデータは一元的に集中管理されるべきであるものの、情報検索の手順や意思決定のプロセス、諸問題の診断などの知識ベースについては、担当者個人、または、少人数グループの情報として蓄積・分散管理されるべきである。個人の固有技術をデジタル情報として蓄積、継承することを支援し、まず担当者にとって意義あるツールを提供できることが重要であろう。担当者が個々に蓄積した情報の中から意義あるものについてはデータベースに適宜選別して登録し、共有できるようにしたい。
5.2 活動モデルと背景情報
5.2.1 業務モデルについての考え方
一般の製造間接業務に関わるモデルとして、活動モデル(activity model)や対象物モデル(object model)がある(H.Suzuki et al.,1996年)。対象物モデルには、製品モデルや物理プロセスモデルなどが含まれる。製品モデルは、CADで作成された形状モデルと属性情報という形で管理されることが多い。また、物理プロセスモデルでは、プロセスシミュレーションモデルや機能評価モデルなどが含まれ、生産の最適化をはかるために重要な役割を果たす。生産計画を立案するためのスケジューリングシステムや射出成形におけるCAEシステムなどはこの範疇に入る(太田雅晴、1994年)。活動モデルは設計や生産準備活動全体のモデルであり、作業手順や担当者、交渉、環境、意思決定背景など様々な要素を含む。一般に、自然法則のみには制約されず、動的なプロセス記述も可能で、検証の根拠がないというような特徴をもつ。B.Mozerら(1997年)は、活動モデルを作業(task)、製品(product)、資源(resources)、人(people)の4つの要素で構成し、距離関数を適用、進化させていく方法論について提案している。また、H.Suzukiら(1996年)は活動モデルと連携して背景情報を利用するためのフレームワークを行っている。
一方、ビジネスプロセスをアクティビティの連結として表現することにより、客観性と再現性のあるビジネスプロセスとの改善手法を創り出そうという試みも行われている(飯島淳一、1999年)。とくに反復的プロセスのスピードアップを図るためにワークフロー管理システムが適用され、一定の効果をあげていることはよく知られている。申請処理や稟議処理、報告書の回覧などは単純なフローの制御で間に合う管理型ワークフローの典型的な事例といえる。この場合に稟議書が書かれた理由や稟議書の内部にある数値の根拠、背景にあるデータ群などには注意が払われない。つまり、稟議書を作成するという業務は管理されず、その稟議書が起案された後、どの部署でどういう指摘を受け、どこまでチェックが進んでいるかという進捗管理に重きが置かれる。
また、環境変化に柔軟に適用できる情報システムの構築を目指して、ビジネス・オブジェクトが開発され、財務会計、在庫管理、受発注管理などの基幹業務を対象に適用が広がっている(J.Martin and J.J.Odell,1998年)。UMLでモデルを記述すればアプリケーションの実装まで支援してくれるツールも普及しつつある。例えば、支援ツールのひとつであるBOMA(片山益男、1999年)では、ビジネス・オブジェクトにprocess、purpose、entity、communityという4つの要素を含み、具体的な業務アプリケーションを構築するための部品として500種類以上のクラスファイルを用意している。但し、製造間接業務で必要な対象物モデルとの関連付けについてはほとんど考慮されていない。また、すべてのビジネス・オブジェクトは予め用意されていなければならないし、エンドユーザのレベルでダイナミックに編集できるものではない。
知的資産管理のためには、(1)知識発見の支援、(2)コミュニティやプロジェクト活動での知識共有の支援、(3)プロセス管理の中での知識共有、再利用の支援に寄与できるツールが必要であるといわれている(幡鎌博 他、1998年)。これらを考慮したモデルが必要である。
5.2.2 活動モデル
ここでは、製造間接業務を表現できる活動モデルについてオブジェクト指向の考え方に基づき以下のように検討した。すなわち、業務とは、連鎖するいくつかの作業を通じて、何らかの意思決定を行い(寸法値を決める、項目を選択する、自然言語で指示を記入する、など)、その結果を図面(形状または注記)あるいは帳票(数値、テキスト、図など)としてアウトプットするものであると考える。意思決定とは何か(値)を決めることであり、その行為は通常何らかの根拠に基づいて行われる。一定のアルゴリズムに基づいて値が決まる場合はそのアルゴリズムをプロシージャに記述しておけば誰でも同じ答えが得られる。しかし、実際の業務では、一定のアルゴリズムに従い自動化処理できるものは少なく、実際には過去の類似部品での経験、文献情報、標準書、ヒアリング情報などをもとにして担当者が値を決定している。一方で、その意思決定の背景になっている何らかの情報が存在することも事実であり、それはその決定された値に対する背景情報の一部であると定義できる。いわゆる「勘で決める」という表現がある。しかし、その「勘で決めた値」でさえ、実は根拠を定量的には説明できないものの、その設計者には何らかのよりどころがあって決定した値であると考えられる。したがって、ある設計者がある時期に何ら陽的な情報に頼らず値を決定したという事実もその決定値に対する背景情報として重要である。
従来、設計意図(Design Rationale)の利用に関して、いくつかの研究が行われており、最近では、H.Suzukiら(1996年) が設計意図の概念をさらに広げた設計背景情報DBI(Design Background Information)についての研究成果を発表し,一般的な部品設計にも応用され始めている。しかし、製造間接業務についてそれらの考え方を適用した例は見あたらない。
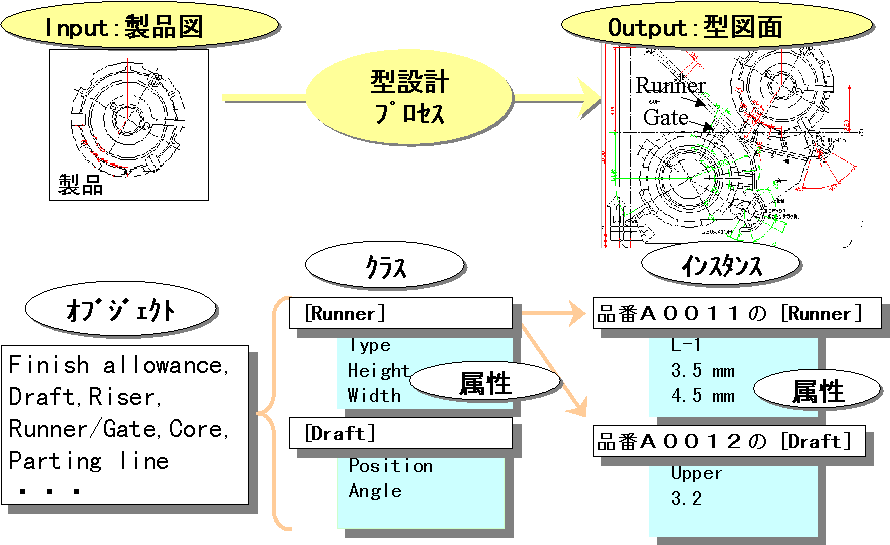
製造間接業務の特徴を十分考えて活動モデルを設計するべきである。例えば、金型設計作業は、ある類似製品のグループ、あるいは、材質ごと、成形プロセスごとに異った形態をもつ。また、金型設計を初期検討、成型品基本設計、金型構造設計、部品図設計という区分に分けて考えることができ、各区分でさらに詳細な設計項目が存在する。たとえば、ランナー・ゲート設計では、位置の決定、タイプの選択、寸法の決定などという詳細作業が含まれる。典型的なオブジェクト指向の基礎概念を参照すると(宇田川佳久、1994年)、これらの設計作業はいわゆるスーパークラスとサブクラスというオブジェクトの汎化関係として整理できることがわかる(図表13参照)。
つまり、あるパターン化された作業連鎖をツリー構造としてモデル化し、クラスライブラリー化することが可能である。いわば、クラスの属性が「決定したい項目」であり、属性値を決定するメソッドとしていくつかの「背景情報」を定義することができる。ただし、背景情報には、メソッドとして機能するものとしないものがある。メソッドとして機能するものとは、プロシージャーが埋め込まれ実行できるものとか、データテーブルを検索して適切な値を決めるなど処理手順が定式化されたものを指す。一方、背景情報には、過去の類似部品の図面や参考文献など、単に参照するだけのものがあり、それらを見て最終的には担当者自身が判断して属性値を手入力することになる。ある値を決定する場合に唯一ひとつのメソッドしか存在しないことはまれであり、複数の選択肢を用意し担当者が選べるようにすることが重要である。
以上より、ここでは最終的に、製造間接業務への適合性、実装の容易性、メンテナンス性を考慮し、階層型の作業項目(Task)と各作業項目において決定すべき項目(形状、作業条件、仕様など)(Design item)、さらに各決定すべき項目と関係付けられた背景情報(標準、計算式、文献、過去の類似部品図面など)(DBI, Design background information)という3つの要素を組み合わせた活動モデルを提案する(長坂悦敬、2000年)。Task、Design item、DBIという3つの要素は、随時、自由に登録、変更が可能で、相互関係をダイナミックに構築したり、修正したりできなければならない(図表15、16)。
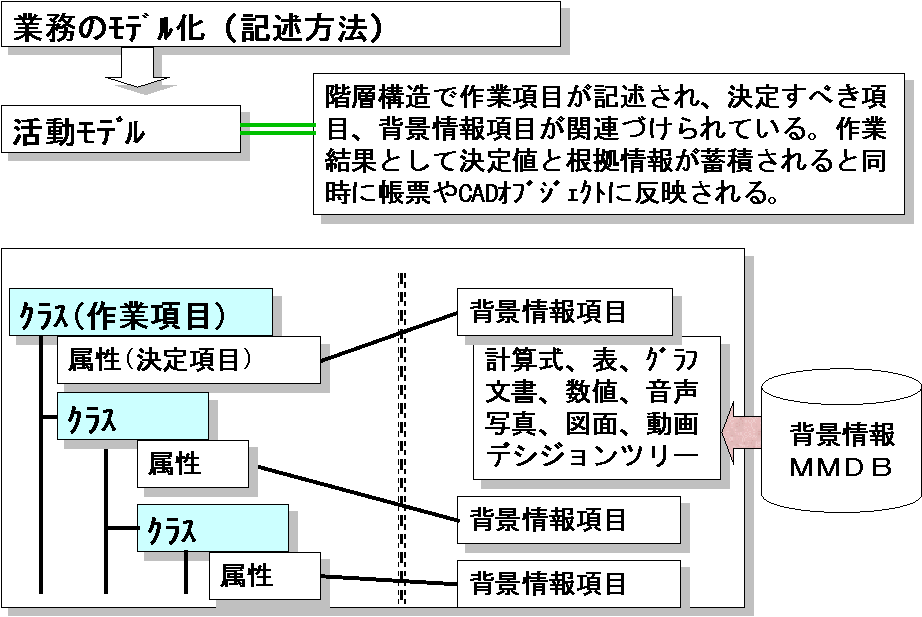
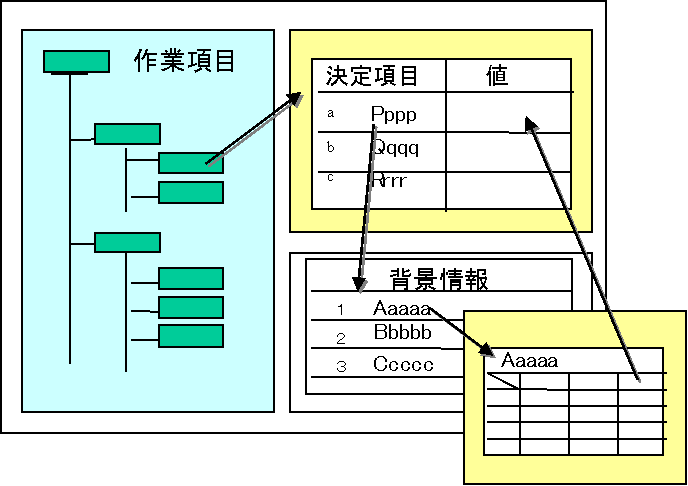
作業項目(Task)はツリー構造で整理され登録される。親になる作業では子になる複数の作業に共通した決定項目(Design item)が存在する。また、ある親項目に所属するものの親項目で共通した決定項目が存在しない場合もある。しかし、親の作業項目から階層を下げた子の作業項目、または、孫の作業項目のどこかには何らかの決定すべき項目が現れる。その決定すべき項目に値を入力していけば、全体の作業が終了するはずである。決定された値はデータベースに格納され、結果として見積書などの帳票、図面、数値表などに形にまとめ上げられる。
決定すべき項目(Design item)に内在するデータとして大項目、中項目、小項目にあたる複数のキーワードとメモ(テキストデータ)が格納されることになる。一方で、社内の技術標準、図面、グラフ、文献など多くのデータが保存されているデータベースが存在し、やはり、キーワードによる管理インデックスが存在する。また、各データの内部にはテキストデータが存在するものもある。したがって、各作業項目(Design item)に登録されているキーワードおよびメモを頼りに関連するデータをデータベースより検索しそのデータ名称を抽出することが可能である。ここで、キーワードのマッチングのみならず概念情報マイニングのエンジンを利用することができ、関連度の高いものからその作業項目(Design item)の背景情報の候補とすることができる。関連度についてはキーワードが一致すること以外に関連語が含まれていることを判断して定量的に表すことができる。現時点では、図面に内在するデータ(形状に関する情報)や画像そのものの中身の情報など視覚的に技術者に参照されるものについてはそれらのデータに付随したキーワードやメモにより関連度を算出するしかないが、今後とくに図面データの関連性を直接形状データから判定していくことも考えるべきであろう。他に、オペレータが意図をもって手作業で背景情報として各種のデータをリンク付けすることも可能である。とくに自動抽出された場合には、その背景情報がその作業項目(Design item )にとって有効である可能性が高いが、各技術者にとって役立つモノかどうかは不明である。実際にこの作業を行うときに個々の技術者がどの背景情報を参照したか、あるいは根拠として採用したかをカウントし、優先度をつけていくことが可能である。決定された値がどの背景情報を参照して、または、根拠として入力されたかについは、すべて作業履歴データとして蓄積されている。振り返って作業を確かめることができるし、製品品質との相関結果から良い作業であると認定できるものが明確になれば、その活動モデルを他の技術者にも参考にしてもらいながらベストプラクティスの構築が可能になるものと期待できる。
この活動モデルを業務で使用した結果として帳票が作成され情報共有が可能となる一方、各作業の回数、所用時間がすべて計測されるとともにすべての履歴がログ情報として記録される。さらに、製品の品質検査結果、クレーム情報、顧客満足度との関係を紐解けば、一連の活動の付加価値を判定できる可能性があり、最終的には図表17に示すようなフレームが構築できる。例えば、業務時間、アウトプット量(帳票、図面、データ、交渉回数・・・)が自動的に詳細に計測される。一方で、生産金額から加工費、材料費、直接労務費、クレーム対策費等の合計を引いた差額を求め、その製品にかかわった間接業務のすべてのアクティビティコストと比較すれば製造間接業務の付加価値が評価できる。さらに、工数が少なく、品質も安定し、材料費も少なくなるような生産設計はどのようなアクティビティの連鎖で行われているかというベストプラクティスの抽出も可能になる。
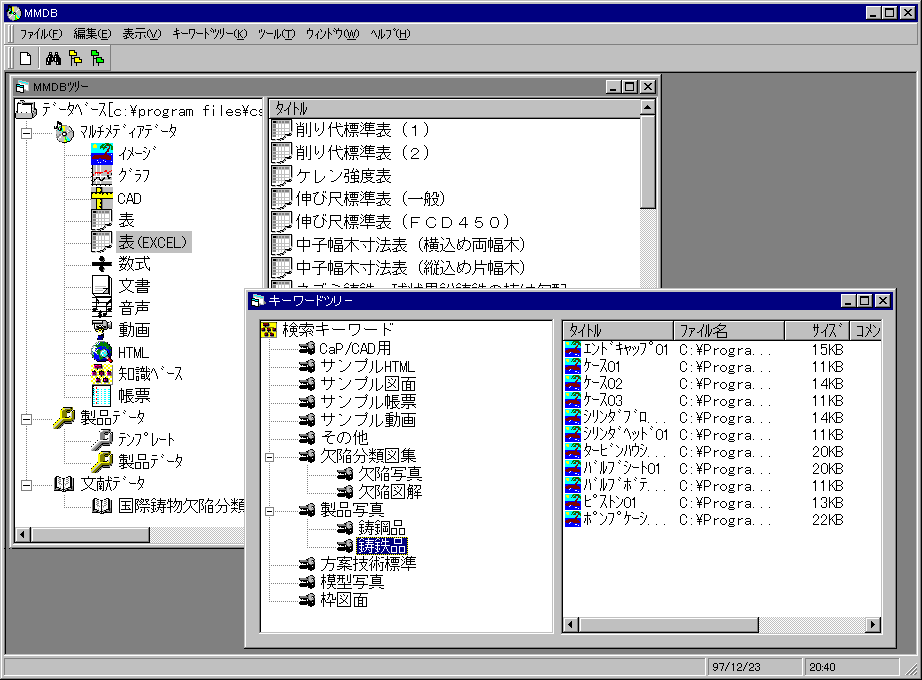
5.2.3 システムの例
上述の活動モデルとマルチメディアデータベース、さらにCADを組み合わせた統合システムの開発し、実務へ適用した。活動モデル登録・変更のためのMMIは、決定値の入力や背景情報の選択にも使用する。つまり、決定値の入力を行いながら、同時に作業モデルを変更することも可能である。実際の画面の例を図表19、20に示す。
操作内容はすべてログ情報として、また、決定値は製品情報の一部として蓄積され、各背景情報の利用回数も記録される。これによって、使用頻度が多い、安定した品質が得られる根拠となる、といった有効な背景情報を選別することが可能である。各作業ごとにその決定値とそれを決定するために適用した背景情報の関係はツリー表示され、後日その生産設計の根拠をひもとくときに参照されるとともに、決定値に誤りがないかどうかチェックするためのリストとしても役立てられる。情報が蓄積され、品質結果と照合されれば、たとえば生産設計標準を改訂し収斂していくことも可能であろう。また、帳票機能を用いてあらかじめ決定項目を必要な帳票へ関連づけておけば、デザインパレットで入力された設計値が自動的に挿入され、作業終了後自動的に帳票が出力される。
このシステムでは、まず(1)情報検索時間の短縮、(2)帳票作成工数の低減、(3)担当者間での情報の共有化、相互啓発、(4)生産設計根拠の明確化と蓄積、伝承という効果が期待できる。さらに、ITを適用することによる業務フローの改善を活動モデルを組み替えるだけで行えるし、そのときにどのような参照物をもって作業が行われていったかという根拠が蓄積されることで固有技術の形式知化が進み、しかも蓄積された形式知を裁量できる環境が提供される。同時に管理会計のアプローチを行い、結果としてABCでいう原価作用因を自動的に計測することが可能となる。まずい金型設計、工程設計、レイアウト設計のために材料費がかかり、MCの稼働時間が長くなり、直接労務費も高くなることがある。付加価値を一義的に定めることは難しいが、材料歩留り、クレーム件数、加工時間などを総合した指標と各アクティビティのコストを比較することで結果的にABMに展開が可能で、動的に活動モデルを改善していくことができる。ベストプラクティスを抽出するためには、各アクティビティと結果との相関を分析しなければならない。データマイニングを応用することが考えられる。定量的な評価指標が出れば、現在のベストプラクティスから更にレベルアップされるように動機づけることも可能になる。いわばベストプラクティス共有型と専門知ネット型のナレッジマネジメントツールとなることが期待できる。
6.まとめ
製造間接業務のコスト低減のために効率化と知的資産管理を並行して支援できる情報システムが必要である。個々人のための形式知の増幅ツールと多くの形式知から有効な情報を抽出する技術によって、情報共有の場の提供、整備(土壌)が実現される。ここでは個人の強みの増幅から組織競争力強化に結びつけるためのベストプラクティス抽出型としてのナレッジマネジメントツールを開発し、実務に適用した。作業時間、回数という直接的な計測値以外に、同時に、知識創造に対する評価基準の明確化も必要で、製造間接業務が生み出す付加価値によって生産性が議論され、プロセスが改善されていくことが大切である。今後、付加価値の定量的計測の可能性について検討していきたい。
参考文献